遺言
「遺言」は相談者様の「最後の願い」を実現する方法の一つです。
事業を引き継いでくれるご子息、お世話になった妻又は夫、子供たち、障害を持たれているお子様などのために遺言をしてみませんか。
相談者様の最後の願いや晩年の幸せな家族生活の実現のために、又は自身のご安心の為、遺言のご相談をお受けします。
尚、一度作成した遺言書は、民法に定める方法により、変更したり撤回したりする事ができます。
また、遺言は、おそらく苦渋の決断になる場合もあろうかと思います。
遺言できる内容
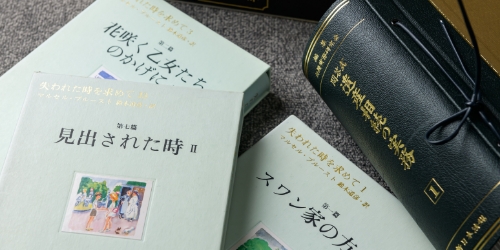
遺言できる内容は、原則として民法などの法律によって定められています。
不動産を長男に相続させ、預貯金を長女に相続される旨の内容などです。
また、相談者様の死後相談者様の遺言を実現する手続きをする人を遺言執行者(ゆいごんしっこうしゃ)といいますが、ご家族や司法書士等をこの遺言執行者に指定することができます。
更に、法的効力はありませんが、付言事項で法律によって定められたこと以外でも遺言の内容とすることが出来る場合があります。例えば、お世話になった妻(又は夫)に感謝の心を表したり、あなたの死後を生き行くご子息を励ましたり、相続人が争いをせず仲良く暮らして欲しいとの意を表すことなどです。
当事務所では、遺言作成後のトラブルをできるだけ回避できるよう、付言事項をできるだけ文書にするように、お取り計らいをしております。
遺言は専門用語や内容に難しいものも含まれるため、詳細はご相談時に必ず分かりやすく説明させて頂きます。
遺言を作成した方が
良いと思われる場合
- 夫婦の間に子供がなく、財産として相談者様の居住用不動産がある場合
- 配偶者やご子息がおられるが、相談者様の死後の配偶者の生活が心配な場合
- 婚姻届を出していない異性がいて、その方に住宅・預貯金などの財産を残してあげたい場合
- 家を継ぐご子息・ご令嬢の1人に、家にまつわる財産を承継させたい場合
- 現在別居中の妻又は夫がいて、離婚届を提出していない場合
- 先妻の子と後妻の子がいる場合
- 小さい時に養子に行った子供がいる場合
- 長男夫婦と同居してきたが、長男の死後、あなたのお世話をしてくれる長男のお嫁さんがいる場合
等
死後の手続-
あなたの死後、遺言の実現の手続を
させて頂きます。
確認
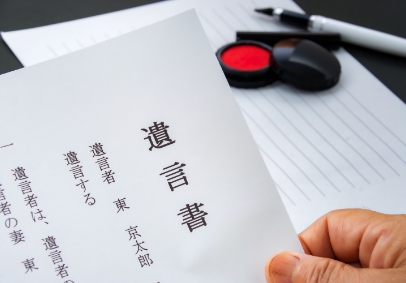
遺言内容の再確認
相続人・関係者へ通知

相続人や関係者に対する通知
書類作成
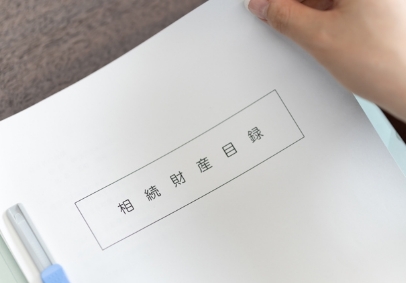
遺産管理着手、財産目録の作成等
報告

執行完了通知、顛末報告
精算

執行報酬等の増減の精算
注)遺言の内容によっては遺留分減殺請求等を受ける場合があります。
遺言に関する
費用について
遺言
(遺言公正証書作成サポート)
原則 16万5000円(税込み表示)~+実費
承認2名の費用を含みます。戸籍類一式、登記簿、名寄帳等必要書類の取得を全て当事務所にご依頼頂けます。
実費
登記簿、戸籍類その他取得実費及び費用
財産が高額な事案、複雑な事案も、初めに見積金額又はその計算方法を提示しています。
事前に見積しますのでお気軽にご相談下さい。
費用は一例です。
正式なお見積りは相談後に
提出させていただきます。

